太陽光発電設備で発生した余剰電力は、電力会社に売却することで収入を得ることができます。この仕組みを支えているのが「固定価格買取制度(FIT)」です。この制度により、導入後10年間は国が一定の価格での買取を保証してくれます。しかし、10年を過ぎると同じ条件での売電は難しくなり、「長期利用には課題があるのでは?」と不安を感じる方もいるでしょう。
この記事では、特に注目される「2019年問題」と、固定買取期間終了後の対応について詳しく解説します。太陽光発電の導入を検討している方にとって、初期費用の回収が可能かどうかや、今購入するメリットが明確になる内容です。
太陽光発電の10年後の課題とは?「2019年問題」を解説
2019年問題とは
「2019年問題」は、2019年に固定価格買取制度の終了を迎える利用者が多数出ることで注目された話題です。この問題は、今後太陽光発電を導入しようと考えている方にも関係があります。なぜなら、制度の背景を理解することで、太陽光発電の仕組みやその後の対応を知ることができるからです。導入後に慌てないためにも、制度終了後のシナリオを把握しておきましょう。
固定価格買取制度(FIT)とは?
固定価格買取制度は、再生可能エネルギーの普及と安定供給を目的として設けられた仕組みです。この制度では、太陽光発電で発生した電力を電力会社が国が定めた価格で買い取ることが義務付けられています。導入当初の2009年には、1kWあたり48円(規模10kW未満)という高額な買取価格が設定されていました。しかし、この価格は毎年見直され、現在(2023年度)の買取価格は1kWあたり16円となっています。
過去の売電価格(1kWhあたり)
| 年度 | 売電価格 |
|---|---|
| 2012年 | 42円(ダブル発電:34円) |
| 2013年 | 38円(ダブル発電:31円) |
| 2014年 | 37円(ダブル発電:30円) |
| 2015年 | 出力制御対応機器なし:33円(ダブル発電:27円) 出力制御対応機器あり:35円(ダブル発電:29円) |
| 2016年 | 出力制御対応機器なし:31円(ダブル発電:25円) 出力制御対応機器あり:33円(ダブル発電:27円) |
| 2017年 | 出力制御対応機器なし:28円(ダブル発電:25円) 出力制御対応機器あり:30円(ダブル発電:27円) |
| 2018年 | 出力制御対応機器なし:26円(ダブル発電:25円) 出力制御対応機器あり:28円(ダブル発電:27円) |
| 2019年 | 出力制御対応機器なし:24円 出力制御対応機器あり:26円 |
| 2020年 | 21円 |
| 2021年 | 19円 |
| 2022年 | 17円 |
| 2023年 | 16円 |
| 2024年 | 16円 |
出典:資源エネルギー庁ウェブサイト
なぜ「2019年問題」が生じたのか?
固定価格買取制度は、導入から10年が経過すると適用外になります。これにより、2009年に制度を利用し始めた56万人以上の利用者が2019年に買取価格の保証を失いました。そのため、「2019年以降の余剰電力はどうなるのか」という疑問や不安が生じ、「2019年問題」として注目されるようになったのです。
2025年時点では、引き続き余剰電力の売電は可能ですが、買取価格が大幅に下がるため、収益性の低下を考慮する必要があります。
制度終了後の10年後にどう対処する?
固定価格買取制度(FIT)の適用が終了すると、売電による収益が減少するため、「最初の10年間しかメリットがない」と感じる人もいるかもしれません。ただ、売電以外にも、自家消費を中心とした効率的な電力活用が選択肢として考えられます。買い取り期間満了後の対策や蓄電池の活用方法について確認していきましょう。
買い取り期間が終了しても売電は可能
FITによる買取期間が終了しても、電力会社への売電を続けることはできます。ただし、以前のように国が定めた一律の価格で買い取られるわけではない点には注意が必要です。
各電力会社が提示する買取価格は異なるため、契約先を選ぶ際には慎重な比較が重要です。特に、1kWhあたりの価格が高いところを選ぶことで収益を最大化できるでしょう。
ただし、ほとんどの場合、買取価格は大幅に減少します。そのため、売電金額だけでなく、売電に付随する特典やサービス内容にも目を向けて選択することをおすすめします。
自家消費を活用して電気代を節約
10年後の売電価格の低下に不安を感じる場合、自家消費を積極的に活用する方法もあります。自宅で発電した電力を家族が使用することで、電力会社から購入する電力を減らし、電気料金を削減できます。
特に、日中の発電量が多い時間帯に家事を行えば、節約効果がさらに高まるでしょう。また、余剰電力を無駄にしないためには、蓄電池を設置するのも有効な手段です。蓄電池があれば、発電した電力を夜間や停電時など必要なときに利用でき、より効率的なエネルギー運用が可能となります。
長期的な視点での活用を
太陽光発電は、導入から最初の10年間は売電収入がメリットとなる一方、買取期間終了後は自家消費を中心とした活用がより重要になります。蓄電設備の導入や電力の使用方法の見直しを行うことで、10年後も太陽光発電を効果的に活用できるでしょう。
💡ポイント
- 買取価格を比較して電力会社を選ぶ
- 自家消費を増やして電気代を節約
- 蓄電池の導入で電力を効率的に活用
太陽光発電を全量自家消費に切り替える際のデメリット
太陽光発電を住宅に導入後、約10年が経過して全量自家消費に切り替える場合、いくつかのデメリットがあります。以下に詳しく解説します。
切り替えに伴う工事費用の発生
全量自家消費型の太陽光発電システムへ変更する際には、さまざまな工事が必要となります。
たとえば、電力会社への売電を停止するための逆潮流防止システムの導入や、配線の変更が必要です。さらに、効率的な電力利用を目指すなら、蓄電池の追加設置も考慮する必要があります。
具体的には、以下のような費用がかかります:
- 切り替え工事費用
- 蓄電池設置費用(一般的には100万~300万円)
これらの初期投資に加え、設置費用の回収時期を考慮する必要があり、費用負担を懸念する方にはハードルとなります。卒FITを迎えた方は、自家消費による節約効果とこれらの費用負担を事前に整理しておくことが重要です。
蓄電池の維持費用が増加
蓄電池を導入する場合、設備の維持管理にかかるコストも考慮する必要があります。
保証期間内であれば、メーカーによるメンテナンス費用が無料の場合もありますが、経年劣化や故障で交換が必要になった際には新規購入時と同程度の費用(約100万円)が発生します。
経済効果と費用負担のバランスを考慮
全量自家消費型への切り替えは、電気代削減効果を期待できる一方で、工事費用や維持費用といった初期およびランニングコストが発生します。これらの費用が家計に与える影響を見極めたうえで、切り替えを検討することが重要です。
💡ポイント
- 全量自家消費に切り替える前に、工事費用や蓄電池の設置コストを計算し、節約効果とのバランスを確認しましょう。
- 初期費用が大きいため、無理のない資金計画を立てることが重要です。
太陽光発電を10年後に自家消費へ切り替えない選択肢
住宅用太陽光発電の固定買取期間が終了する11年目以降、自家消費以外の運用方法を選ぶことも可能です。以下では、自家消費以外の選択肢について詳しく見ていきます。
太陽光発電の撤去を検討する
太陽光発電システムの維持管理費が負担となったり、経済的メリットが薄れたりした場合は、撤去するという選択肢もあります。
撤去費用は設置規模や業者によって異なり、住宅用では足場設置や撤去作業、廃棄物の運搬処理費などを含めて数十万円が目安です。
ポイント
- 維持費や破損リスクを解消できる。
- 非常用電源を失うデメリットがある。
非常用電源が必要な場合は、蓄電池や小型ソーラーの導入で代替案を検討することも可能です。
産業用太陽光発電への移行を検討
売電収入を重視する場合、住宅用を撤去して「野立て型」の産業用太陽光発電に切り替える方法もあります。
産業用は50kWや100kWなど、住宅用より大規模な出力を確保でき、50kW以上の場合は全量買取が適用されます。
メリット
- 大きな発電量により、年間100万円以上の売電収入が期待できる。
- 副収入を得たい人に適している。
ただし、初期費用が高額なため、費用回収の期間や返済計画をしっかりシミュレーションすることが重要です。
卒FIT後も電力会社へ売電を継続
固定買取期間が終了した後も、電力会社の提供するプランで売電を続けることが可能です。たとえば、東京電力の再エネ買取標準プランでは、1kWhあたり8.5円(税込)の単価が設定されています。
比較ポイント
- FIT制度中の売電価格(例:16円/kWh)と比較すると単価は下がる。
- 売電収入を生活費に充てたい場合にはメリットがある。
卒FIT後も非常用電源として活用できる点は、引き続き検討する価値があるでしょう。
選択肢を考える上での注意点
いずれの選択肢を取る場合でも、初期費用やランニングコスト、メリット・デメリットを総合的に判断することが大切です。家庭の状況や目的に合った最適な方法を選びましょう。
太陽光発電を導入するなら今がチャンス!
現在(2025年1月時点)、太陽光発電をこれから導入しようと考えている方にとって、心配する点はほとんどありません。特に影響を受けやすいのは、2015年以前に導入した方々です。これから導入を検討する場合は、初期費用の回収を見据えた計画を立て、適切な運用環境を整えることが重要です。
2019年問題は新規導入者には無関係
太陽光発電をこれから設置する場合、かつて話題になった「2019年問題」を気にする必要はありません。卒FIT(固定価格買取期間終了)を迎えた事例を参考にすることで、10年後を見据えた準備を進められる今の方が、むしろ有利な状況ともいえます。
FITによる売電価格は下降傾向にありますが、2025年度の1kWhあたりの買取価格(10kW未満のシステム)は16円と、ここ数年で大きな変動は見られません。将来的に2019年問題のような影響が発生する可能性はゼロではありませんが、現時点では深刻に考える必要はないでしょう。
初期費用は回収できる可能性が高い
「初期費用を回収できないのでは」と心配する声もありますが、FIT終了後の売電価格が下がっても、多くの場合、費用回収は十分に可能です。
太陽光発電システムの寿命は30年以上とされ、定期的なメンテナンスを行うことで、それ以上の利用も期待できます。仮に導入後10年間で費用を全額回収できなくても、11年目以降も適切に運用を続けることで、収益化を実現することができます。
太陽光発電が費用回収を可能にする理由
太陽光が無限に供給される再生可能エネルギーであることが、費用回収の大きなポイントです。導入時期が早ければ早いほど、その分長期的な利益が期待できます。また、太陽光発電は環境負荷が少ないため、エコロジーな選択としても評価されています。
定期的なメンテナンスを怠らず、適切に運用すれば、導入費用の回収は難しくありません。放置することなく適切に管理することで、投資した以上の価値を引き出すことが可能です。
💡ポイント
- FIT終了後も事例を参考にして10年後の計画を立てる
- 買取価格は下降傾向だが大きな変動はない
- メンテナンスを続ければ、長期的な収益化が期待できる
太陽光発電を導入する魅力とは?
太陽光発電は、自然のエネルギーを活用して電力を生み出すシステムです。環境に配慮しながら電気代の節約にもつながるという、経済面と環境面の両方で多くのメリットがあります。まだ導入を検討中の方に向けて、その魅力を詳しくご紹介します。
経済的なメリット
太陽光発電の大きな特徴は、 売電収入 と 電気料金の節約 を同時に実現できる点です。家庭で使いきれない電力は電力会社に売ることで収益を得ることができます。FIT(固定価格買取制度)が終了した後も、希望すれば電力会社との契約を継続し、売電を続けることが可能です。
- 導入直後から節約効果を実感
発電した電力を家庭で利用することで、電力会社から購入する電気が減り、月々の電気代を削減できます。特に晴天が多い日中に多くの電力を発電するため、昼間に電気を多く使う家庭ではより大きな節約効果が期待できます。 - 日中の電力利用が多い家庭に最適
在宅勤務や日中に家にいることが多い家庭では、発電量を効率的に活用できるため、さらに経済的な恩恵を感じやすいでしょう。
環境に優しい選択
太陽光は枯渇する心配がない再生可能エネルギーです。発電時に二酸化炭素などの温室効果ガスを排出しないため、環境負荷をほとんど与えません。
- 地球温暖化対策の一助
世界的な課題である地球温暖化に対して、再生可能エネルギーの活用は重要な取り組みです。太陽光発電はその一環として、環境保護に大きく貢献します。 - 次世代に向けた選択
太陽光発電を導入することで、持続可能なエネルギー活用の実現に寄与できます。家庭で環境問題への意識を高めるきっかけにもなり、社会全体の環境配慮の推進に繋がるでしょう。
💡まとめ
- 経済面:売電収入と電気料金の節約で、家計に優しい
- 環境面:地球温暖化対策や持続可能な社会への貢献
- 将来性:長期的にメリットを享受できるシステム
太陽光発電は、導入すればするほどその価値を実感できる選択肢です。経済的にも環境的にもメリットの大きい投資として、前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
蓄電池も合わせて導入するのが賢明な理由
太陽光発電を導入する際、 蓄電池を同時に設置する ことで、さらなるメリットを得られます。蓄電池は節電効果を高めるだけでなく、停電時の電力供給にも役立つため、生活の安定性を向上させます。ここでは、蓄電池のメリットや補助金制度について詳しく解説します。
電気料金をさらに節約
蓄電池は、太陽光発電で作った電力を貯めておく設備です。これにより、雨の日や夜間など太陽光発電ができない時間帯にも、貯めておいた電力を使えるため、電力会社から購入する電気を減らせます。
- 太陽光発電だけの運用よりも高い節約効果
蓄電池を併用することで、日中に発電した電力を効率的に活用できるため、さらに電気代を節約できます。 - 適切な機器選びが重要
家庭で使う電力量と発電量に合った蓄電池を選ぶことで、無駄なく活用できます。発電・蓄電のシミュレーションを行い、最適な設備を選択することが大切です。
災害時にも安心
蓄電池に貯めた電力は、地震や台風などの災害で停電が起きた際に使用できます。太陽光発電と組み合わせることで、災害時も電力を確保できる点が大きな魅力です。
- 停電中でも電力供給が可能
電力会社からの電気供給が止まっても、太陽光発電と蓄電池があれば、自宅で発電した電気を使えるため、停電への備えとして安心感があります。 - 供給時間は蓄電量次第
蓄電池の容量や消費電力に応じて、供給可能な時間は異なりますが、一時的な電力不足を防ぐには十分な対策となるでしょう。
補助金制度を活用してお得に導入
蓄電池の導入には、国や自治体の補助金制度が利用できる場合があります。補助金を受けるためには、太陽光発電設備の設置が条件となることも多いので、事前に対象条件や補助金額を確認しておくことが重要です。
- 自治体ごとの支援内容を確認
地域によって支援金額や条件が異なるため、事前に調べてお得に導入する方法を検討しましょう。
まとめ
太陽光発電は「導入初期のメリットだけ」と思われがちですが、長期的に見ると初期費用を回収できるうえ、設備の寿命が長いため、固定買取価格制度終了後も効果を発揮し続けます。
蓄電池を併用することで、さらに電力の自家消費が可能になり、売電価格が下がった場合でも家計への影響を抑えられます。災害時にも役立つため、より安心した暮らしが実現できます。
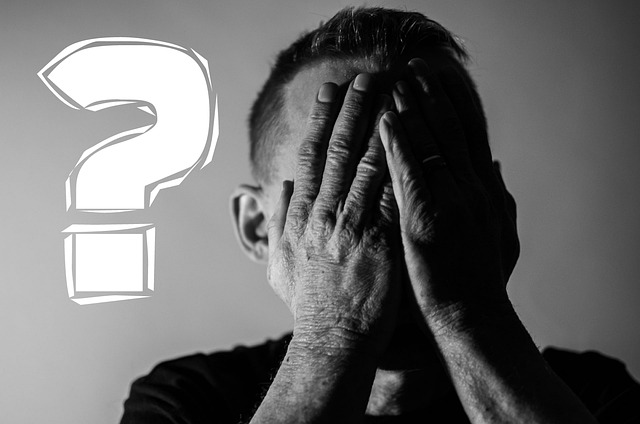


コメント