戸建てを新築する際に、太陽光発電の導入を検討する方は少なくありません。「新築時に設置するのがいいのか、それとも後から追加で設置するのがよいのか」「それぞれのタイミングでどのような違いやメリットがあるのか」といった点に悩むことも多いでしょう。
この記事では、太陽光発電の設置タイミングごとの特徴やメリット、設置にかかる費用について詳しく解説します。これを読むことで、自分にとって最適な導入タイミングが見つかるはずです。
太陽光発電の設置はいつがベスト?
住宅を新築する際は大きな出費が伴います。そこに太陽光発電を設置する費用を追加するとなると、さらに予算が必要です。そのため、太陽光発電を新築時に設置するのか、あるいは後付けにするのか迷う方もいるかもしれません。それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、事前にしっかり比較しておくことが重要です。以下では、新築時と後付けのそれぞれの利点を詳しく見ていきましょう。
新築時に設置するメリット
新築時に太陽光発電を設置する主なメリットは以下の通りです:
- ローンを一本化できる
太陽光発電の設置費用を住宅ローンに組み込むことができ、支払いがスムーズになります。 - 発電効率が向上する
新築時であれば、太陽光パネルの設置を考慮した屋根の形状にすることが可能です。これにより、効率よく発電できる設計が実現します。一方で、後付けの場合は既存の屋根形状が発電に向かないこともあり得ます。 - 初期費用を抑えられる
後付けでは追加の施工が必要になるケースが多く、新築時よりも費用が高くなる場合があります。また、パワーコンディショナなどの設備も、新築時に設置を計画しておけば、より効率的に導入が可能です。
後付けするメリット
後付けで太陽光発電を設置する場合の主なメリットは次の通りです:
- 固定資産税がかからない
新築時に屋根一体型の太陽光発電を導入すると、住宅の一部として固定資産税が発生する可能性があります。しかし、後付けの場合、架台を使って取り付ける形式が主流であるため、通常は固定資産税の対象外となります。 - 柔軟なタイミングで設置できる
後付けは、中古住宅を購入した場合や、屋根のメンテナンス工事を行うタイミングで導入すると、トータルコストを抑えられる場合があります。
- 販売店の比較検討がしやすい
後付けで太陽光発電を設置する場合は、自分で販売店や施工業者、さらには太陽光パネルのメーカーまで自由に選べます。そのため、複数の見積もりを取り寄せて相場を確認し、費用が安い販売店を選んだり、施工実績が豊富で信頼できる業者に依頼したりすることが可能です。
新築時に太陽光発電を設置する費用について
新築住宅に太陽光発電を導入する際、費用について正確に把握しておくことが重要です。ここでは、初期費用、維持費、メンテナンス費用の3つに分けて詳しく解説します。
初期費用
太陽光発電システムの導入費用は、設置するシステムの発電容量によって大きく異なりますが、目安として 100万円から300万円 程度を想定してください。初期費用が高額に思えるかもしれませんが、太陽光発電の耐用年数は約30年以上とされています。適切なメンテナンスを行えば、長期にわたり使用できるため、費用を回収できる可能性が高い設備です。
さらに、太陽光発電には 固定価格買取制度(FIT) があります。家庭用の小規模発電(10kW未満)であれば、10年間にわたって売電価格が固定される仕組みで、これを活用すれば初期費用の回収が一層容易になります。
【住宅用太陽光発電の固定価格買取制度:調達価格の推移】
| 年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調達価格(円/kWh) | 42円 | 38円 | 37円 | 33円 | 31円 | 28円 | 26円 | 24円 | 21円 | 19円 | 17円 | 16円 | 16円 |
| 調達期間 | 10年間 | ||||||||||||
維持費・メンテナンス費用
太陽光発電システムは、設置後も定期的な点検やメンテナンスが必要です。具体的にどのような費用がかかるのかを見てみましょう。
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 定期点検費用 | 3~4年に1回の定期点検が推奨されています。2017年施行の改正FIT法により、「保守点検・維持管理」が義務化され、専門業者への依頼が必要です。 |
| 故障対応費用 | 太陽光発電システムが故障した場合、多くのメーカーや施工業者は保証を提供しています。保証期間内であれば、無償対応となるケースがほとんどです。 |
| その他の費用 | 基本的には点検費用以外の維持費は発生しません。ただし、外部要因によるダメージが発生した場合は別途費用がかかる場合もあります。 |
故障時の保証について
太陽光発電システムが故障するリスクを心配する方も少なくありません。しかし、ほとんどのシステムには保証が付帯しています。特に、耐用年数を大幅に下回る時期での故障については、保証により無償で対応されることが一般的です。
メーカーや施工会社によって保証内容は異なる場合がありますが、標準的な耐用年数の範囲内であれば、初期費用を十分に回収できる可能性が高いでしょう。
太陽光発電を新築時に導入する際は、こうした費用構造をしっかりと理解した上で判断することが大切です。適切な計画を立てれば、長期的に見て大きなメリットを享受できるでしょう。
太陽光発電を導入するメリットとは?
太陽光発電システムを設置することで得られるメリットは、売電収入だけにとどまりません。非常時の電力供給など、さまざまな場面で役立つ可能性があります。ここでは、太陽光発電の主なメリットについて詳しく解説します。
売電による収益
太陽光発電の大きな魅力の一つは、自宅で発電した電気を売ることができる点です。設置に初期費用がかかりますが、固定価格買取制度(FIT) により、家庭用の発電(10kW未満)は10年間、売電価格が一定に保たれます。
| 年 | 1kWあたりの売電価格 |
|---|---|
| 2020年 | 21円 |
具体的な収益は発電量や家庭での電力使用量によって異なるため一概には言えませんが、一般的には10年程度で初期費用と維持費を回収できるとされています。このため、投資回収が難しいリスクは比較的低いといえるでしょう。
固定価格買取制度の適用が終了する10年後も、売電による収入は続きます。たとえ買取価格が下がったとしても、初期費用を回収していれば、それ以降は利益を得やすいと言えます。
非常時の電力確保
太陽光発電は災害時の電力供給手段としても大きな役割を果たします。地震や台風などでライフラインが遮断される事態が起きても、発電中の日中は自家発電した電気を利用することが可能です。
非常時に使える電力があるだけで、生活の負担を大幅に軽減できます。特に停電が長引く場合、太陽光発電は大きな助けとなるでしょう。
太陽光発電は、日常のエネルギーコスト削減だけでなく、非常時の備えとしても大きな価値を持つシステムです。これらのメリットを最大限に活かすため、導入時には自宅の条件や設置環境をしっかり検討することが重要です。
新築時に太陽光発電を導入する流れ
新築住宅に太陽光発電を導入する際の一般的な流れを確認しておきましょう。設置にあたっては、保証面や技術的な観点からも、専門知識を持つ設置業者に依頼することが推奨されます。ここでは、工務店と太陽光発電設置業者を別々に手配する一般的な流れを紹介します。
工務店との契約と同時に設置業者を手配
太陽光発電の導入を決めたら、住宅を建築する工務店との契約と同時期に、太陽光発電設置業者とも契約を結びましょう。このタイミングで契約することで、住宅の設計段階から太陽光発電システムを考慮したプランニングが可能になります。
ただし、工務店側がこちらで手配した太陽光発電設置業者との調整に対応できるか、事前に確認しておくことが重要です。
スケジュール調整
住宅の建築には複数の業者が関与するため、太陽光発電システムの設置時期を工務店やその他の業者と調整する必要があります。一般的には、工務店と設置業者が連携してスケジュールを組んでくれますが、機器の設置場所確認などのために、設置業者が建築現場に何度か訪問することもあります。
完成と入居準備
補助金を活用する場合は、住宅の完成時期が補助金申請の期限に間に合うか確認しておくことが大切です。補助金申請を代行してくれる設置業者であれば、工務店との調整もほぼお任せできますが、建築主自身も手続きに関与する場面が出てくるため、進捗状況をしっかり把握しておきましょう。
入居とアフターケア
補助金申請、電力会社との売電契約、そしてFIT(固定価格買取制度)の認定が完了すれば、いよいよ入居となります。その後、定期点検を確実に実施するために、契約書や保証書は必ず保管しておきましょう。こうした書類があれば、トラブル時やアフターサポートの際も安心です。
以上が、新築時に太陽光発電を導入する際の主な流れです。事前準備をしっかり行うことで、スムーズに設置を進めることができます。
太陽光発電設置で失敗しないためのポイント
太陽光発電の設置は売電によるメリットが期待できますが、適切に計画を立てなければ十分な効果を得られない可能性もあります。ここでは、損をしないための具体的な注意点を解説します。
売電収入を正確に把握する
太陽光発電で損を避けるには、売電収入の見積もりを正確に把握することが重要です。固定価格買取制度が適用される期間内であれば、収入の予測が立てやすくなります。以下の3つの点を考慮して計算しましょう。
- 地域による発電量の違い
日照条件や気候の違いで発電量は地域ごとに変動します。導入前に正確なシミュレーションを行うことが必要です。 - 業者によるシミュレーション精度の違い
設置業者によるシミュレーションは精度が異なるため、計算基準を確認しましょう。豊富な導入実績がある業者ほど、正確な予測を期待できます。 - 固定買取期間内の初期費用回収
初期費用が固定買取期間内に回収できない場合、その後の買取価格が大幅に下がるリスクがあります。このため、期間内で回収可能か事前に計画を見直すことが大切です。
費用以外のサポート内容にも注目
導入時には費用面だけでなく、アフターサポートの内容にも目を向けましょう。太陽光発電システムは修理費が高額になることがあり、サポートが不十分な場合には思わぬ出費が発生する可能性があります。
- よくある故障事例
モジュール内部の故障、断線、接続不良などが代表的です。これらは施工ミスや自然災害によるものが多く、リスクを完全に排除することは困難です。 - 故障の発見が遅れるリスク
太陽光パネルは屋根の上に設置されるため、異常が起きても目視で確認しにくいことがあります。日常的にメーターをチェックすることが大切です。 - 保証と点検サービスの充実度
定期点検を行い、手厚い保証を提供している施工会社を選ぶことで、故障時の対応がスムーズになります。
信頼できる業者を選ぶ
太陽光発電を導入する際、業者選びは成功の鍵を握ります。極端に低価格を提示する業者の中には、技術力や知識が不足している場合もあるため注意が必要です。
- 考えられるトラブル
施工不良により太陽光発電システムが正常に動作しない、屋根の取り付けが不適切で雨漏りが発生するといった事態が起こる可能性があります。 - 業者を見極めるポイント
相談時の対応、見積書の内容や価格、売電シミュレーションの精度などを総合的に比較して判断しましょう。
以上の点に注意して計画を立てることで、太陽光発電設置の失敗を防ぎ、安心して導入することができます。
太陽光発電を成功させるためのポイントまとめ
太陽光発電を導入する際、新築時に設置するのか、後付けで設置するのかで選択肢や条件が異なりますが、どちらの場合でも以下のポイントを押さえることで、損をせずにメリットを最大化できます。
- 事前シミュレーションで収支を明確に
地域や設置条件に応じた発電量の予測を行い、固定買取期間内での費用回収計画を立てることが大切です。 - サポート内容を重視して安心を確保
修理や点検がしっかりしている業者を選ぶことで、トラブル時にもスムーズな対応が期待できます。 - 信頼できる業者選びを慎重に
価格だけでなく、施工実績やアフターサービスの充実度を比較し、安心して任せられる業者を選びましょう。
これらのポイントを踏まえた上で、太陽光発電を導入すれば、環境への貢献だけでなく、経済的なメリットも長期間にわたって享受できるでしょう。計画的に進めることで、暮らしにさらなる価値を生み出す太陽光発電の魅力を最大限に活用してください。
地球温暖化対策の一環として、家庭での再生可能エネルギー導入が推奨されるようになり、約20年が経過しました。その中心となるのが太陽光発電設備であり、普及を支えてきた固定価格買取制度(FIT)の単価は年々低下しています。しかし、それと同時に設備導入のコストも大幅に下がっているため、現在でもFIT期間内で費用を回収できる状況が続いています。
また、新築住宅に太陽光発電を併せて設置することで、光熱費の削減や災害時の停電対策といった多くの利点を得ることが可能です。
この記事では、新築時に太陽光発電を導入する際のメリットについて解説し、失敗しないための注意点や利用できる補助金制度についても詳しく説明します。さらに、最近話題の東京都における設置義務化についても取り上げますので、新築住宅での太陽光発電を検討中の方にとって有益な情報をお届けします。
太陽光発電を新築時に設置するメリットは?
まずは新築時に太陽光発電を導入した場合のメリットを解説していきます。
FIT制度の認定で得られる売電収入
新築時に太陽光発電を設置する大きなメリットの一つは、FIT制度(固定価格買取制度)の対象となり、売電収入を得られる点です。
この制度は、再生可能エネルギーの普及を目的とした国の支援策で、住宅用太陽光発電によって生み出された電力のうち、家庭で使いきれなかった分を電力会社に買い取ってもらえる仕組みです。特に、10kW未満の住宅用設備の場合、10年間にわたり固定価格で余剰電力を買い取ることが保証されています。
【住宅用太陽光発電の固定価格買取制度:調達価格の推移】
| 年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調達価格(円/kWh) | 42円 | 38円 | 37円 | 33円 | 31円 | 28円 | 26円 | 24円 | 21円 | 19円 | 17円 | 16円 | 16円 |
| 調達期間 | 10年間 | ||||||||||||
このように、普及が進むにつれて買取価格は下がっていますが、設備の導入コストも同様に低下しています。そのため、売電収入で導入費用を回収することは依然として可能です。また、売電収入や自家消費による光熱費の削減を活用すれば、余った資金を住宅ローンの返済に充てることもできます。
自家消費スタイルへの転換も視野に
固定価格での買取期間(10年間)が終了した後は、売電をやめて蓄電池を活用し、余剰電力を家庭の夜間需要に回す「完全自家消費」型の運用が増えつつあります。これは電力会社との任意買取が安価になるケースが多いためです。
新築時に太陽光発電を導入する場合、初めから将来的な自家消費を見据え、蓄電池を併せて設置するプランを検討することが重要です。このように、売電収入を活用しつつ、買取期間終了後の対応も見越した計画を立てることで、長期的に安定した電力運用が可能となります。
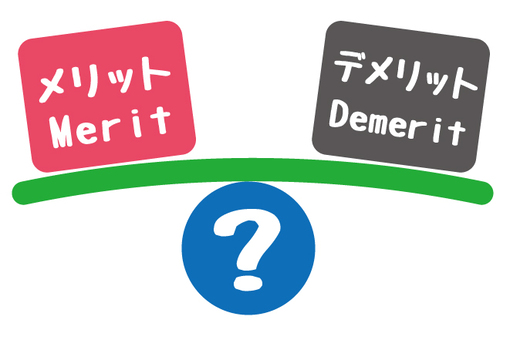


コメント